脱炭素を製造業の社内に浸透させるクラウドサービス「エコいっぽ」
第141回 かわさき起業家賞
会社紹介
私が20歳のとき、世の中に大きな変化が訪れました。Windows 95が登場し、MicrosoftやYahoo!といった企業の名前が急速に広まり始めたのです。当時、大学の情報工学科に在籍していた私はその状況を目の当たりにし「これは面白い、すごいことが起きている」と強く感じました。そして「自分もこの流れに乗って、社会を変えるようなことをしたい」と思うようになったのです。
しかし、当時の私は普通の理系学生だったので、何をどう始めればいいのか分かりません。そこで、さまざまな業界の経営を学ぶため、就職先として大手コンサルティング会社を選択しました。その後、転職を経てシンガポールに赴任。世界中から多様な人々が集まる環境で多くの起業家と出会い、刺激を受けました。そして37歳になったとき、そのままシンガポールで、はじめての会社を立ち上げました。
その後、いくつもの事業を進めてきましたが、一貫して取り組んできたのは世界が共通して抱える課題の解決です。2019年にbajjiを立ち上げ、環境問題へ挑むことに決めたのも、その想いがあったからでした。「テクノロジーの力で世の中を1mmでも良くする」というパーパスのもと、日本から世界に届くサービスを創っていきます。
基本情報
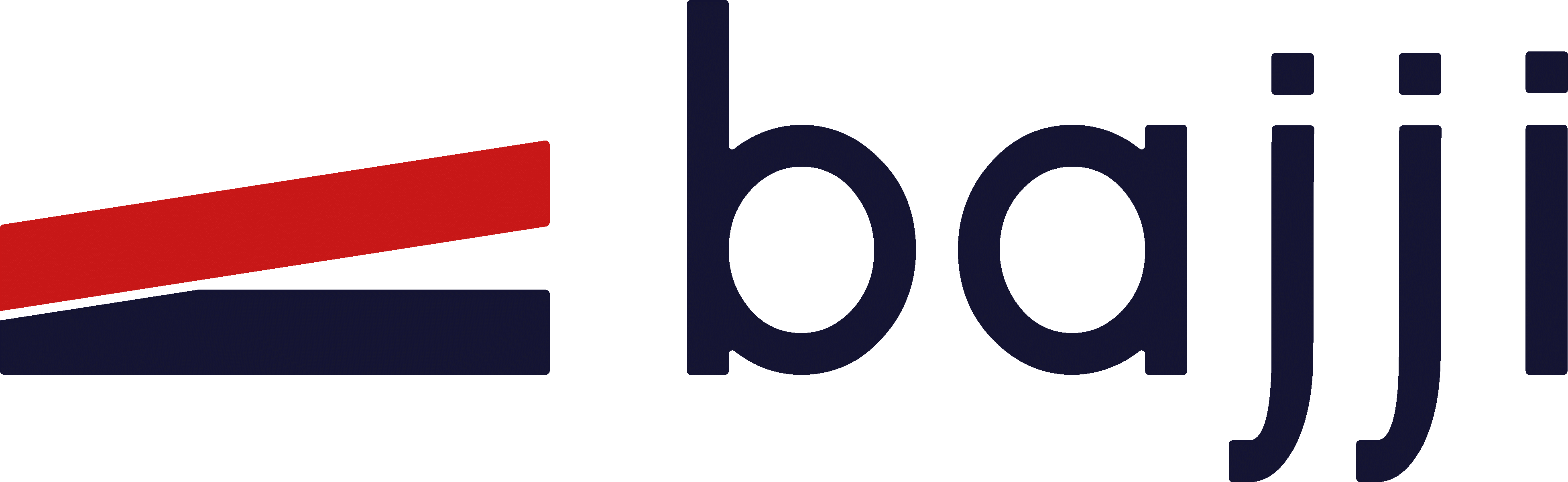
株式会社bajji
〒111-0052
東京都台東区柳橋2丁目1番11号
Barq SHINSO BLDG 403
受賞したビジネスに至った経緯
2021年に、ビル・ゲイツが『地球の未来のため僕が決断したこと』という本を出版しました。その中で特に印象的だったのが「510億からゼロへ」という言葉です。この数字は、当時の年間CO2の排出量(世界)で「アフターコロナの次に取り組むべき最も重要なテーマだ」と強調していました。しかし「510億トン」という想像もつかない数字を、本当にゼロにできるのか?という疑問を感じたのです。当時の私は環境問題にそれほど詳しくなく、世界で何億トンのCO₂が排出されているのかさえ知りませんでした。私が知らないということは、世界のほとんどの人も知らないはずです。この状況を変えるために必要な最初の一歩は「みんなにこの問題を気づかせること」だと考えました。そして、その実現には、目に見えないCO₂排出量の「見える化」が不可欠だと思い至りました。この発想が、「エコいっぽ」を生み出すきっかけとなったのです。
当初は、CO₂の削減量を見える化しながらポイントを貯めて楽しめる、一般ユーザー向けのサービスとして提供していました。ところが、このサービスが広がりを見せると、法人のお客さまから「これを社内向けに導入できないか」という予想外の声がかかるようになりました。そこで法人向けにカスタマイズしたところ、特に製造業のお客さまから多くのお問い合わせをいただくようになったのです。
製造業における課題の一つが、本社と現場の間で発生する環境問題への温度差です。というのも、本社では経営会議などを通じて頻繁に環境問題に触れていますが、そうした機会が少ない工場の現場は、CO₂削減への関心が低い傾向にあるからです。しかし製造業にとっては工場こそが最大のCO₂排出源であり、対策を講じなければならない場所です。
そこで、現場の人たちが無理なく楽しく参加できる取り組みとして「エコいっぽ」が注目されるようになりました。実際にご利用いただいているある製造業のお客さまからは、工場内での脱炭素への意識が大きく高まったという声をいただいています。
サービスの特徴

企業が脱炭素化を進める上で「再エネへの転換」や「設備投資」は、費用をかければすぐに効果が見える取り組みです。しかし、それだけでは不十分で、社員一人ひとりが意識を持ち、行動を変化させることが欠かせません。そのため、社内でエコイベントを開催したり、社内ポータルで情報発信をしたりする企業もありますが、参加率の低さや継続の難しさに悩んでいるところも多いです。
「エコいっぽ」は、こうした課題を解決できるサービスです。大きな特長は、従業員が楽しみながらエコアクションを実践できる仕組みを持っていること。自社のCO₂削減量が一目で確認できたり、脱炭素に関するクイズに挑戦したりしながらゲーム感覚で参加できるため、意識しなくても環境問題に関する知識が身につき、行動が変わっていきます。実際に導入いただいた企業では、7~8割の高い継続率を実現しており、定着しやすいことが大きな強みです。
現状の課題
当サービスでは「工場でどれだけCO₂を排出しているのか」「どれだけ省エネに成功しているのか」といったデータをリアルタイムで取得し、従業員がすぐに確認できる環境の提供を目指しています。しかし企業によっては、そういった指標自体は存在するものの、データの更新が月に1回程度にとどまり、リアルタイムでの取得が難しいケースも少なくありません。そのような状況では、たとえ私たちが「見える化」の仕組みを構築しても、十分な価値を提供できないという課題が生まれてしまいます。
とはいえ、環境に関するあらゆるデータをリアルタイムで可視化することは難しく、その実現に全力を注ぐのは効率的ではありません。そこで私たちは「本当に重要で、取り入れるべきデータ」に焦点を絞り、価値あるデータだけを適切に活用できる環境を整えることに注力していきたいと考えています。
また「エコいっぽ」をお客さま企業に浸透するまでには3ヶ月から1年ほどのリードタイムが必要です。この期間中、当社エンジニアの業務負担が一時的に減ってしまうことが課題となっています。そのため、エンジニアがやりがいを持てるようなリソース配分や適切な人員配置を検討し、さらに成長の機会をどのように創出していくかも、今後の重要なポイントとなりそうです。
今後の展開
私たちは、この「エコいっぽ」を製造業界のスタンダードとして定着させることを目指しています。そして最終的には、エコ活動を共有できる“情報シェアプラットフォーム”となり、企業全体の環境意識を高められる存在になっていけたら理想的です。
事業を発展させていく上での最終的な選択肢としては、IPOやバイアウトが一般的かもしれません。しかし私は「世界に爪痕を残すこと」をゴールに据えています。これには、17歳の時に訪れたドイツでの体験が深く影響しています。街中に降り立った私の目に映ったのは、パナソニック、ソニー、トヨタなど、日本を代表する企業のロゴが光るネオンサインでした。それを見た瞬間、「いつか自分も世界に影響を与えることができたら」と強く思いました。そんな少年時代の私のように、未来の中学生や高校生が海外を訪れ、私のつくったサービスのロゴを目にする。そんな瞬間を生み出すことが私にとってのゴールであり、IPOやバイアウトはその先にある選択肢です。これからも、このビジョンを実現するために挑戦を続けていきます。
パートナー企業との連携で実現したいこと

受賞後は、製造業のみなさんから少しずつご連絡をいただくようになりました。川崎市をはじめ、神奈川県には多くの製造業の工場があると思いますので、そうした方々に「“エコいっぽ”を試してみたい」と思っていただけたら、これほどうれしいことはありません。ものづくりの街・川崎市のネットワークを活用させていただきながら、少しずつ広がりをつくっていけたらと考えています。新しい出会いをとても楽しみにしています。


